20代の頃は時代小説が好きで、様々な作家のものを読み漁っていたことがあります。けれども、気が付けば読書からも遠ざかる日々。そんな私が久しぶりに手に取った時代小説が、西條奈加の『まるまるの毬(いが)』(講談社文庫)でした。
なお、記事中にはネタバレを含みますのでご注意ください。
『まるまるの毬』とは?
『まるまるの毬』とは、南星屋(なんぼしや)という菓子屋を舞台とした時代小説です。
南星屋で働くのは、主人の治兵衛・娘のお永・孫のお君の3人。
皆で協力しながら店を切り盛りする仲良し家族なのですが、そのような家族にだって生きているからには良いこともあれば悪いこともありますよね。
また、治兵衛は出生に秘密を持つ身。時にはそれが家族に良くない影響を与えるなどということも起こります。
けれども、南星屋の家族たちはお互いを思いやりながら波風を乗り越えていきます。その姿にほっこりとした気分になりました。
現代にも共通するような出来事が起こる
これまで私が読んできた時代小説は、八丁堀の関係者が出てくるタイプのものがほとんどでした。だから、裁判沙汰になるような明らかな事件が起こるものが多かったのです。
しかし、この小説はそうではありません。南星屋の人々に起こる身近な出来事がメインです。
・南星屋が菓子の製法を盗んだのではととがめられる。
・弟子入り希望の武家の少年とその父親との親子のしがらみに巻き込まれる。
・お君の縁談に際して家族がそれぞれの思いを抱く。
・南星屋や治兵衛に対しての嫉妬心を抱く老舗菓子屋の主人の企みに振り回される。
盗作騒ぎや縁談の際のあれこれは今でもありますよね。また、他の出来事についても同様です。まったく同じのことはないにしても、親子関係で問題を抱く人から頼られるとか嫉妬されて嫌な態度を取られるみたいなことは起こり得ます。
この小説の舞台は、江戸時代というすでに歴史となっている遠い昔。けれども、そこで生きる人々の気持ちは今も昔も変わらないのだなと改めて感じました。
お永に感情移入をする
この小説を読んだ時に、私が最もその言動に感情移入したのは南星屋のお永でした。治兵衛の娘であり、お君の母にあたる彼女。南星屋の3人の中では、目立たずに一歩引いて家族を支えているという存在です。
しかし、そのお永が激しく心情を吐露するのが、文庫本のタイトルにもなっている「まるまるの毬」という章です。その心情が語られる程に「わかるわかる」と頷きたくなりました。
秘された事実がそこにあった
お永は元亭主の浮気が原因で別れてから、娘のお君を連れて実家の南星屋に帰っていました。その後、元亭主とは完全に縁が切れていたのです。
ところが、お永と元亭主がこっそり会っていたことがお君にバレてしまいます。お君にとっての父親は、自分と母親を捨てていった憎むべき相手。二人が会っている現場に突入したお君は、父親にひどい言葉を投げかけてしまうのです。また、そんな人と会っていた母親のことも許せません。
それも仕方がないですよね。お君は多感なお年頃。父親の浮気が原因での別れとなると、複雑な感情が出てくるのをとがめることはできません。
しかし、お永には誰にも打ち明けていなかったことがありました。それは、浮気騒動後に「やはり一緒に暮らしたい」と元亭主が南星屋を訪ねてきたことです。
私の中のお永のイメージ
お永は控えめだけれどもとても懐の深い人だと思うのです。自分から激しく主張することはあまりありません。けれども、自分の軸をしっかりと持っていて、人の気持ちをよく理解して受け止めることができるような印象です。
このタイプの人は許容範囲が比較的広めですよね。でも同時に、これだけは許せないという絶対的な領域がはっきりしているとも思うのです。一度そこに踏み込んだ時には、いつも穏やかなあの人がここまで拒否するなんてと周囲が驚いてしまうことも珍しくありません。
「なのにあたしは、許さなかった……亭主の浮気なぞ世間ではよくあることだと、頭ではわかっていたのに、どうにも気持ちがこじれて、あの人を許すことができなかった!」
西條奈加・『まるまるの毬(いが)』(講談社文庫)
亭主の浮気が珍しくない世の中であったとしても、自分の亭主のこととなると許してはおけないことだったのでしょう。復縁の話があってから約6年。誰にも言わずに自分の胸の内にしまい込んでいたところに、お永の苦しさが見え隠れして切なくなりますね。
自分を責めなくてもよいのに
別れの原因は元亭主の浮気だったわけですが、お永という人はそれでも彼を責めることはありません。
「あたしはずっと、あの人ひとりを悪者にして、知らぬ存ぜぬを通してしまった……この六年、どれほどそれを悔いてきたのか」
西條奈加・『まるまるの毬(いが)』(講談社文庫)
最初に傷つけられたのはお永です。元亭主の方も許してもらえないという事実に苦しんだのかもしれませんが、それはあくまでも自業自得。自分が蒔いた種なのですから、自分で気持ちの落としどころを見つけてもらえばよいのです。
けれども、元亭主を悪者にしてしまったと悔いるお永の姿。そんなに自分を責めなくても良いのにと読んでいて思ったのですが、お永にはもっと深い思いがあったようです。
「親を憎むなんて、何より辛いことなのに、それをお前に強いてしまった。ごめんなさい……ごめんなさい……、お君……」
西條奈加・『まるまるの毬(いが)』(講談社文庫)
自分がすべてを話さなかったがために、娘に恨みの種を与えてしまったこともお永は悔いていました。
元亭主を許す許さないはひとまず置いておいて、事実を一言だけでも家族に伝えていたとしたら確かに結果は違ったのでしょう。けれども、それができないほど当時のお永には苦しかったから言えなかったわけで……。
葛藤から見えるお永のカッコよさ
このように自分を責めるお永を見て、彼女が弱い人間だと感じた人もいるのではないでしょうか? けれども、私にはそうは思えませんでした。
お永が心情を話す場面では、彼女の心の葛藤が痛いほどわかってつらくなることがあります。しかし、表面上は弱音に見える言葉の裏側にカッコよさを感じることもありました。
自分の大切な人が傷つくよりも自分が傷つくほうがよい。皆が幸せに過ごせるのなら痛みは全部引き受ける。
言動の端々にそのような強さや心意気を感じるんですよね。そこに魅力を感じるので、私はお永に感情移入をしながら読んだのでしょう。
南星屋の人たちにまた会いたい
時代小説というと、歴史に興味がなければ理解できないのではと思っている人もいるかもしれません。けれども、菓子屋の家族に起こった出来事が書かれているので、現代小説しか読んだことがないという人にも読みやすいかと思います。
また、南星屋の人たちは家族仲が良くて、それぞれにタイプは違うけれども優しい人の集まりなんですよね。だから、読み終わった後もほのぼのとした温かい気持ちになります。
また、南星屋の人たちに会いたい。
そう思っていたら、このお話はシリーズもののようですね。嬉しい情報です。そう遠くないうちに続きも読もうと思うので、また記事にした際はお付き合いください。
〈関連記事〉
【読書記録】『御宿かわせみ』所収~「初春の客」~・平岩弓枝
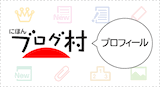

.png)